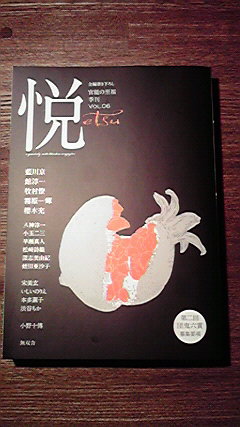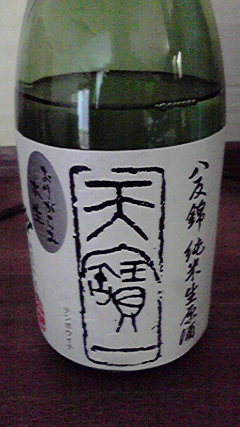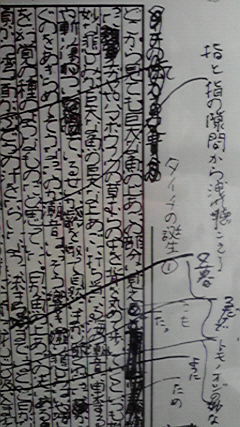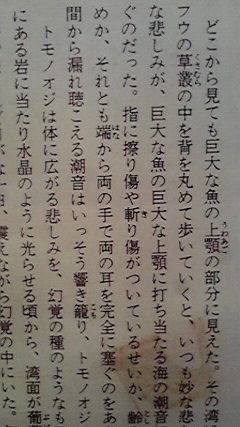2011.11.11
将棋が大好きです。
将棋を指すのも好きですが、それ以上にプロが対局した将棋を観るのが大好きです。
ネットの発達でありがたいことに、最近はタイトル戦や順位戦(棋士の序列を決める、棋士の生命線とも言っていい棋戦。その年のトップ棋士が名人に挑戦できる)がリアルタイムで観戦できるようにもなりました。
私がプロの対局を好きなのは、棋譜の向こうにプロ棋士の人間性や魅力が垣間見えるからに他なりません。
つまり、プロの将棋に惚れる以上にプロ棋士に惚れているのです。
今をときめく羽生喜治が若かりし頃、「将棋は人間性を反映しない」と言い切ったことがありますが、それは違う、というより、そうあって欲しくないという思いでいっぱいでした(今の羽生将棋はまさしく羽生先生の生きざまを存分に反映していると思っていますが)。
例えば大好きな加藤一二三。
大食漢で対局日は昼夜とも食事が同じメニュー、常に股下までの長いネクタイ、好調を意識すると止まらぬ咳払いなど様々なエピソードを持ち、愚直なまでに一本気な加藤は、当時の中原名人にどれだけ負け続けても同じ戦法を貫き通し、最後は念願の名人位をもぎ取りました。
例えば米長邦雄。
米長は南芳一とのタイトル戦の際、「横歩も取れない男に負けてはご先祖様に申し訳ない」と言い放ち、挑発に乗って横歩を取った南を執念で押さえ込みました。
また米長の「自分にとっては消化試合であっても相手が重要な対局の時こそ全力で相手を負かさなければならない」という米長イズムは、今や将棋界の常識となっています。
余談ですが、以前上田市民会館で米長先生が講演会を開いた時、妻と一緒に楽屋にアポなしで訪問した際に頂いた「化粧よりほほえみ」と書かれた色紙は今でも大切な宝物です。
最近で記憶に新しいところでは、アマチュアからプロ棋士に転進を遂げた瀬川晶司。
プロ棋士の登竜門である将励会を規定の25歳までに抜け出せず一度は挫折したものの、アマチュアとしてプロ棋士に勝ちまくっていた成績が評価され、前代未聞のプロ昇格試験でプロ棋士6人に合格ラインの3勝を挙げて見事プロ棋士の座を勝ち取った時の棋譜とニュースは、将棋界を超えて社会現象にまでなりました。
そして私の大好きな谷川浩司。
21歳で史上最年少の名人となったこの将棋界のプリンスは、50歳を目前にとした今もなお凛としたオーラを発し続け、その清楚な立ち振る舞いと輝きは彼の将棋にもそのまま反映されて、多くのファンを魅了しています。
ここのところしばらく停滞しておりますが、ぜひまたタイトル戦に登場してファンの心を鷲づかみにしてほしいものです。
そうそう、思い出しました。
結婚前、まだ将棋の「し」の字も知らない妻に何とかプロ棋士の美しさを見せたいと思い、玉砕覚悟で千駄ヶ谷にある日本将棋連盟に観戦希望の手紙をしたためたところ、何とOKの返事が来てびっくり。
指定の日時に訪れた将棋連盟の特別対局室で、たった5分ではありますが王将線の決勝リーグ、「米長邦雄ー森けい二」を観戦できたことは大切な思い出です。
最後に。
「名人」と並ぶ将棋界の最高タイトル「竜王」。
この「竜王」になると賞金はいくらもらえるかご存知ですか?
答えは何と4200万円。
びっくりでしょう?
この「竜王」を弱冠27歳の渡辺明が7連覇中で、今まさに8連覇を賭けて元名人の丸山忠久と7番勝負の真っ最中です。