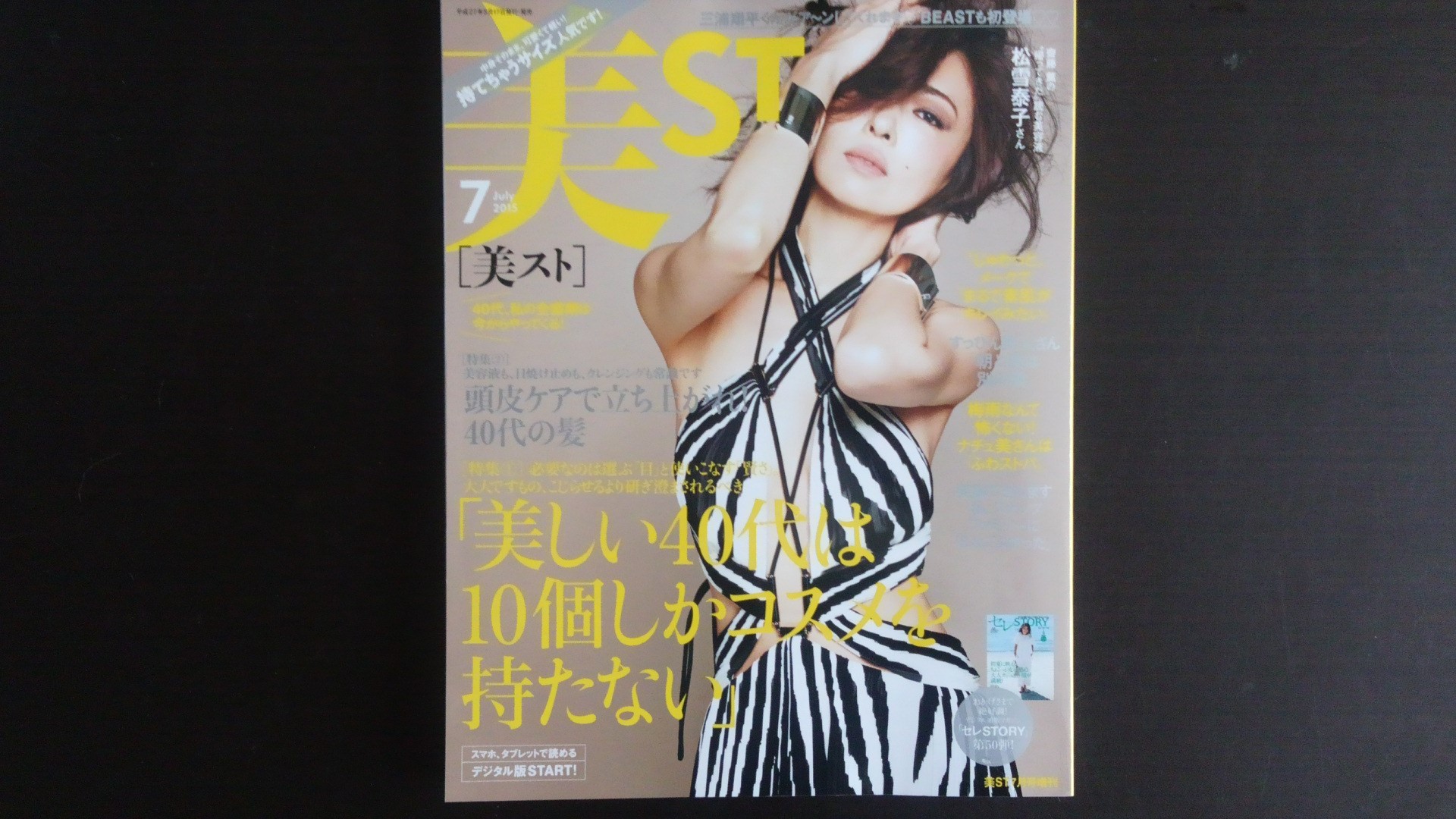都内のとあるホテルのロビーフロアにあるカジュアルレストラン。
私はここで取る朝食が大のお気に入りです。
なぜならばスタッフにTさん(女性)がいるからです。
彼女はサービスの達人です。
約1年ぶりの訪問となったこの日も、入口で目が合った瞬間に私の名前を呼びながら笑顔で出迎えてくれて、彼女自ら私が大好きな窓際の席に案内してくれました。
「昨日チェックインされたところを拝見しましたので、今朝はいらっしゃるのではないかとお待ちしていたのですよ」
何て素敵な出迎えのひとこと。
確かに前日チェックインの際、レストランをチラッと見た瞬間に入口に立つ彼女の姿をとらえたのですが、まさかあの時気が付いていてくれたとは・・・。
続いて、私が腰を落ち着かせたところを見計らって
「ところで今日はオムレツはどうされますか?」
打ちのめされました(笑)。
このレストランの朝食は基本的にバイキングで、もちろん普通のオムレツもあるのですが、それとは別に裏メニューとして「白身のオムレツ」なるものが存在するのです。
真っ白なオムレツに緑色のハーブのソースが添えられた、舌だけでなく目も楽しませてくれる一品です。
その存在を知ってからはずっとその「白身のオムレツ」がお気に入りで頼むのですが、彼女は今日もそれにするかと聞いてくれているのです。
それにしても1年ぶりの訪問ですよ。
何でここまで覚えていてくれるのか、驚きと感激とで、今日も心をわしづかみにされた自分がそこにいました。
その後はゆっくりと食事を楽しんで、立ち去る前にどうしてもTさんにひとことお礼を言いたくて、彼女の手が空いたところで声を掛けました。
「実は今日もTさんに会えることを楽しみにして伺ったのです」と伝えると、何と彼女、「こんなこともありましたよね」と、これまで私が訪問した際のエピソードをいくつか思い出して語ってくれたのです。
彼女は自分のサービス、自分の笑顔で人を喜ばせることが大好きなんだろうなあ。
そんな思いを抱きながらレストランをあとにした、とても心地よい朝でした。