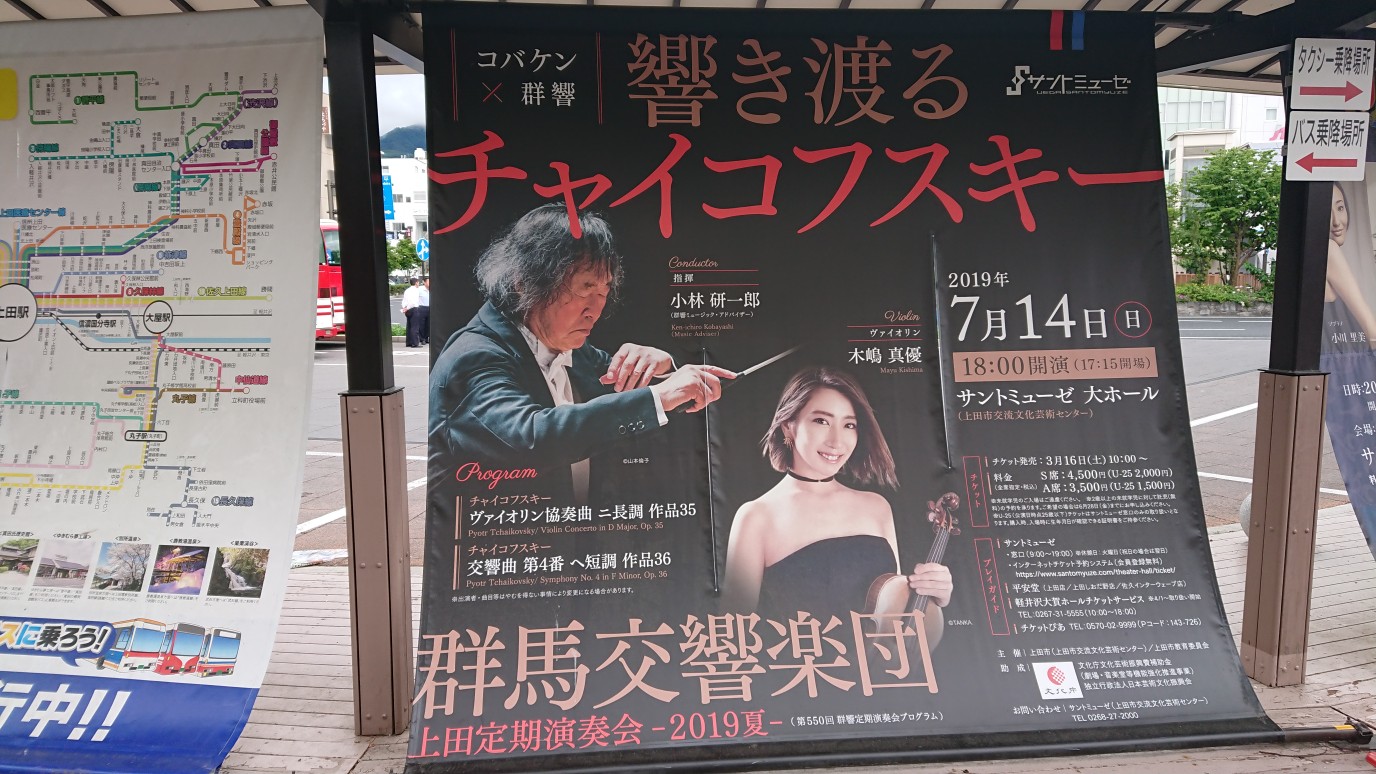深夜にブルーレイで北野武監督「3-4X10月」(「さんたいよんえっくすじゅうがつ」)を久々に観直しました。
傑作です。
監督デビュー作「その男凶暴につき」に続いて北野武がメガホンを取ったこの作品は、客が入らず興行的には惨敗でした。
しかし続く「ソナチネ」も含めて、北野監督の初期3作が個人的には大好きでたまりません。
いわゆる北野ブルーといわれる映像美。
観客をあえて無視して独走し続けるストーリー展開。
北野作品ならではの静寂さと間。
例えば柳ユーレイとダンカンとたけしと愛人が沖縄の海岸で野球に興じるシーンや、続く「ソナチネ」でやはり沖縄の海岸でたけしはじめ部下たちが相撲をはじめ余興で時間を潰すシーンは、あえて「退屈」で「冗長」な場面を挟み込むことで、逆説的に映画全体に比類なき緊迫感を生んでいるという意味で、極めて重要です。
また、この映画ではBGMの音楽が一切流れません。
エンドロールも、登場人物たちが何事もなかったかのように草野球を楽しむ歓声とボールの音だけをBGMとして淡々と流れていく、その「動」を喚起させる「静」こそが、この作品全体のイメージを象徴しているといえるでしょう。
一転して次の「ソナチネ」では、多くの北野作品を手掛けることになる久石譲を初めて起用したことも、北野武のその異才ぶりを痛感させられます。
たけしが自分の愛人を押しのけて部下の渡嘉敷勝男と強引に関係を持とうとするシーンなどは、意外性に驚きながらも、この意外性は逆にビートたけし本来のリアリズムであり、このシーンだけかえって安心感を覚えてしまうことからも、「3-4X10月」ひいては北野ワールドの、あまりに強烈で劇薬的な魅力に気付かされるのです。