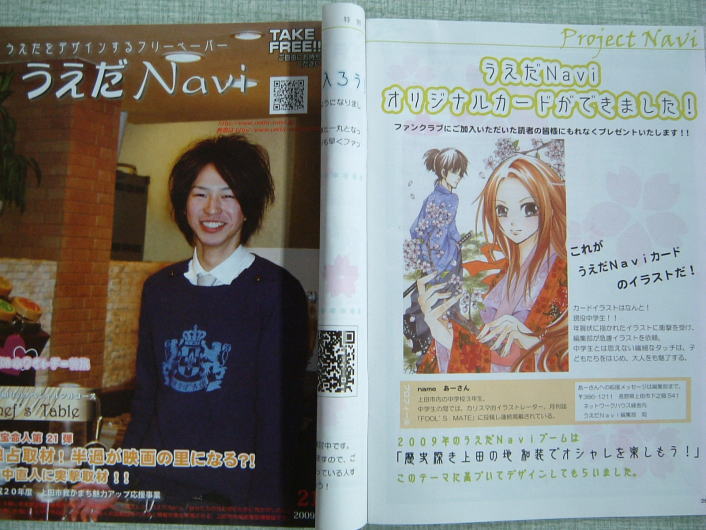「酵母」は微生物です。
自然界にはそれこそ数え切れないほどの酵母が生息していて、その中から清酒製造に合った酵母が選び抜かれて「清酒酵母」として使用されます。
次に、清酒製造における「酵母」の役割をおさらいします。
米中の主成分である「デンプン」は、麹菌が生成する糖化酵素によって「ブドウ糖」に分解されます。
そしてその「ブドウ糖」を取り込んで、「アルコール」と「炭酸ガス」に変える(=アルコール発酵)のが「酵母」の役割です。
その「酵母」はどうやって手に入れるのですか?という質問をよく受けます。
回答ですが、大多数の蔵元は「日本醸造協会」が培養・頒布する、いわゆる「きょうかい酵母」を使用しています。
またその他に、県の研究機関が独自で開発した酵母を使用する場合もありますし、また蔵元が自社のお蔵から自ら酵母を分離して使用しているケースもあります。
長野県でも10年以上前に県独自の酵母として「アルプス酵母」が開発され、今でも日々改良が加えられています。
さて日本醸造協会が分離・培養するその「きょうかい酵母」、ひと口に「きょうかい酵母」といってもその性質によっていくつもの種類があります。
香りはどんな香りでどのような立ち方をするか、酸はどれくらい生成するか、アルコールの発酵力はどれだけあるか、味わいはどのように仕上がるか・・・言い換えれば、自社の製造条件や最終的に求める酒質に合った酵母をしっかりと選ぶことが大切です。
古くからあるもので有名な「きょうかい酵母」としては、長野県の宮坂酒造から分離・培養され現在もオールマイティに使われている「きょうかい7号」、熊本県酒造研究所で開発され吟醸系酵母として名高い「きょうかい9号」、仙台国税局の小川鑑定官室長が分離した「小川酵母」の名前でも知られ淡麗な酒質を生み出す「きょうかい10号」などが挙げられます。
またよく目にする「きょうかい701号」「きょうかい901号」「きょうかい1001号」といった「末尾に「01」が付く酵母は、それぞれの酵母を変異させた「泡なし酵母」です。
もろみや酒母で高泡が発生しないように改良された酵母で、高泡が出ないことによる作業の平易化という利点がある反面、泡の状態を目で見て判断するという旧来からの五感による方法を用いることがてきないという短所もあります。
今は「きょうかい酵母」の半数以上を「泡なし酵母」が占めています。
また最近では、新しい「きょうかい酵母」として分離あるいは認定される酵母も次々に誕生しています。
秋田県が開発し、日本酒の芳香成分のひとつであるカプロン酸エチルを多く生み出す「きょうかい1501号」、同じくカプロン酸エチル高生産性で酸の生成が少なく、近年とみに使用する蔵元が増えている「きょうかい1801号」などがその一例です。
酵母だけがお酒の味わいを決めるわけでは決してありませんが、ラベルに記された酵母の種類を確認しながら飲む一杯も、ちょっとだけお酒に対する知的好奇心が増した気がして楽しいかもしれません。