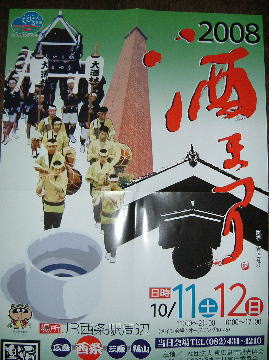
毎年10月に行なわれている東広島市の「酒まつり」、今年も10月11日(土)・12日(日)に開催され、弊社も出品します。
平成2年から始まったこのイベント、会場の西条中央公園には全国の地酒約900銘柄が一同に集まり、例年20万人が来場するという、そのスケールの大きさに圧倒されます。
日本で唯一お酒に関する国の研究機関である「独立行政法人 酒類総合研究所」があることでも知られる東広島市、酒どころ広島県が活況を呈している様子が伝わってきますが、実は私にとっても広島県は大変思い入れが深い場所であります。
と申しますのも、私が公私ともどもお世話になっている若手の蔵元が何人か広島県にいらっしゃるのです。
福山市「天寶一(てんぽういち)」、呉市「宝剣」、東広島市「富久長」、東広島市「加茂金秀」、これらの蔵元がその方々なのですが、皆さん経営者兼杜氏あるいは製造責任者として日々邁進されています。
私がこの方々と知り合ったのは数年前なのですが、いつもお目にかかるたびに日本酒に掛ける思いや製造技術のあれこれを教えて頂き、そして話すたびにたくさんの勇気と元気を頂戴しております。
毎年一度は、以前このブログでもご紹介した上田市の隣に位置する青木村田沢温泉「ますや旅館」に皆さんお越し下さり、名湯や素晴らしい料理を堪能しながら公私入り混じっての様々な話題で盛り上がります。
逆に2年前には、ぜひ一度広島まで勉強に来ないかというお誘いを頂いて私が広島の地に赴き、皆さんの蔵をひとつひとつ見学させて頂きながらたくさんの事を学ばせて頂きました。
かような訳で、私にとって広島とは、またひとつ思い入れの深い県であります。
余談ですが、尾道市を見下ろすようにそびえる山の頂上にある千光寺公園、そこから眺めた瀬戸内海の素晴らしい景色は忘れません。
