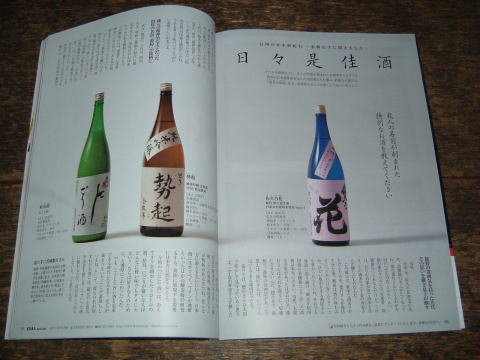3月16日付の「日刊ゲンダイ」に「いまが旬 酒粕のソコヂカラ」という記事が掲載されていました。
酒粕は以前から健康食としてよく知られ、その効用はあちこちのメディアで取り上げられていますが、今回の記事ではそれを更に細かく掘り下げて言及しています。
ちなみに酒粕とは、お酒を搾った時にもろみから分離される固形分です。
ですからお酒の成分がたっぷりと詰まっています。
通常、分離されたばかりの酒粕は板状です(「板粕」と呼びます)。
酒造り最盛期の冬から春に掛けては、この板粕が売りに出されます。
またこれらの板粕を槽に詰め、空気を抜くために足でよく踏み込み、初夏までそのまま置いて粕中に残存している酵母の力で自然発酵させ、泥状になった粕を「踏み込み粕」といい、こちらは初夏以降に流通し、主に漬物用に使われます。
さて、その「日刊ゲンダイ」の記事より抜粋します。
「酒粕はアミノ酸をバランスよく含み、ビタミンやミネラルが豊富な点も広く知られていて、その栄養価は”サプリメントにも負けない”といわれるほど」で、「低カロリーの上に、タンパク質、炭水化物、食物繊維、ビタミンB1、B2、B3、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛などさまざまなビタミン類やミネラルを含むので、中年族の健康維持に良いのはいうまでもありません」。
「健康効果はこれだけでなく」、「麹には骨の分解を抑制する成分が含まれており、骨粗しょう症にいい。血液サラサラ効果やコレステロール上昇抑制作用も確認されているので動脈硬化防止にもプラス」で、「比較的多く含まれるカリウムには血圧を上昇させない働きがあり、また酒粕はインスリンの急激な上昇を抑えるので糖尿病の食事療法にも役立っています」。
「酒粕、おそるべしではないか。機能性食品を越えるパワー、これが酒粕の底力なのだ」。
清酒、ひいては酒粕を扱う我々蔵元にとっては何とも力強い記述が続きます。
そんな中、私も日頃から酒粕を販売していて一番多い質問がその調理法。
今回の「日刊ゲンダイ」の記事ではその点も取り上げています。
その中から、特に簡単にできる代表的なものを抜粋して紹介致します。
「粕汁…ダシ汁の中に野菜とサケ、酒粕を溶かしていれるだけ。食塩はほとんどいらない。」
「山家(やまが)鍋…ブタ肉、野菜をいっぱい入れた鍋に酒粕とみそ同量を溶かし入れて出来上がり。体が温まる。」
「漬物…みりん、食塩、酒粕をよく混ぜてキュウリなど野菜を漬ける。1~2日置いて手でぬぐう程度で酒粕も一緒に食べる。ぬか漬けより塩分は少なめだ。」
さあ、今まで酒粕に触れたことがなかった方もぜひ一度お試しになりませんか?