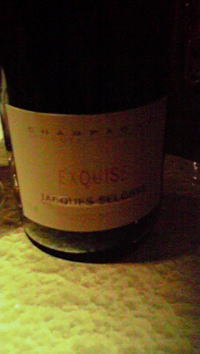2010.07.20
相変わらず飲み続ける毎日です。
家に居れば居たで、いつもの習慣で他の蔵元のお酒をずらりと並べて片っ端から飲み倒し(勉強にもなるし何より楽しいのです)、外に出たら出たで1軒では飽き足らず、余力があればお気に入りの居酒屋やバーをハシゴする繰り返しです(ただし財布の余裕もあれば、の話ですけど)。
外で飲んだ時は、この辺で切り上げようと思っていても、結局はお酒や仲間の魅力に負けてしまい、気が付いたら日付が変わっているという事もしばしばです。
先日もこんな事がありました。
その日は月に一度の定例の飲み会で、男ばかり11名、いつもの居酒屋でどんちゃん騒ぎで盛り上がり、重い腰を上げたのが午後9時過ぎでした。
私もかなり酩酊してはいましたが、その足で以前このブログにも登場した近くの割烹「海鮮処・祭」へ。
ただし今日は飲むためではなく、近々開く宴会の予約をするために出向いたのでした。
ここ連日飲み会が続いた事もあり、さすがに今日はすぐに帰ろうと決意をして、お店のご主人と女将に要件だけを告げお店をあとにしようとしたところ、思わぬ話題で3人で花が咲いて、しばらく立ったまま歓談。
そうこうしているうちに「一杯飲んでいきなよ!」というご主人からの誘惑に負けて、結局はカウンターに座って飲み始める事と相成りました。
ちょうど宴会のお客様も引けたあとで、ご主人が調理して下さる旬の食材を肴に舌鼓を打ちながらグイグイと杯を重ね、うしろ髪を引かれながら席を立ったのは午後11時過ぎでした。
無事帰宅し、一風呂浴びて寝ようとしたところ・・・明日の早朝までに準備しなければならない買い物にハッと思い付いたのが運のツキ。
いつもならば明朝買い物に出向けばいいと冷静な判断が下せるのですが、そこは酔っ払いの勢いというもの。
気が付けば24時間営業のスーパーに向けて、再度自転車を漕ぎ出しておりました。
そのスーパーまでは自転車で約20分、決して短かい道のりではありません。
しかも、今あとにしたばかりの上田の夜の繁華街を再度突っ切らなければならないのです。
こういう時は偶然が重なります。
こちらも先月のブログに登場した「レストランバー・リビアーモ」のオーナーが、ちょうどお客様のお見送りで外に出てきたところにバッタリ遭遇。
さすがにその時は「ちょっと買い物があって」と事情を説明して、そのまま買い物に向かいました。
しかし現金なもので、いざ買い物が済んで安心すると、先ほど彼と会ったのも縁とばかりに、気が付けば買い物袋を提げたまま「リビアーモ」のドアを開けておりました。
「今日は一杯だけで帰るから」そう告げて、「レッドアイ」(ビール&トマトジュース)をキューっと空け、それではお勘定と思った矢先・・・ここでまた出来事が。
先程からカウンターの2席向こうでひとりで飲んでいた常連の女性が、スタッフの女性と囁いているのが聞こえてきます。
「あちらにいるのは和田さん?」
ギクリとしながら、さり気なくその女性の顔を窺ったところ・・・見覚えがありません。
誰だろうと思案していると、そのスタッフの女性が「和田さんの高校時代の部活の後輩との事です」と伝えてくれました。
高校卒業以来15年以上ぶりの再会、しかも女性とくれば、それは分からなくても仕方ない事と自分自身を納得させます。
そして彼女と挨拶を交わしたのですが、彼女は私を試しているのか、笑うだけで自分の名前を名乗ってくれないんですね。
後輩とだけ告げられて、1年下か2年下の後輩なのかも分からない。
それでも女性の名前を間違ること許されまじと、私は酔った頭をフル回転させて、当時の後輩の名前をひとりひとり記憶の彼方から呼び起こします。
表面上は平静を装ってはいても頭の中はフルスロットルです。
しかし酔いが頭の回転を妨げます。
そしてようやくひとりの後輩の名前に絞り込んで、勇気を出して恐る恐る「あなたは××さん?」。
間違ってました・・・爆。
いくつかのヒントでようやく彼女の正体(?)が分かってみると、紛う方無き高校時代の面影を残すNさんでした。
名前を間違った後ろめたさと、しかし本当に久々に会話を交わす楽しさとで、帰るはずだった私はまたカクテルを注文し、しっかりと腰を落ち着けていたのでした。
そんなこんなで時刻は深夜0時過ぎ。
帰途に付く準備をし始めたNさんを見て、今度こそ私もお暇(いとま)をと思った矢先、お店のドアが開いて入ってきたのは、以前から顔は知っていたもののこのお店で話をして俄然仲良くなったFさん。
「和田さん、隣いいっすか?」と、私とその後輩の間に座り、彼の楽しいトークが一気に炸裂します。
私はといえばいつの間にかスコッチをストレートで何杯も煽り、後輩のNさんをお見送りしたあともFさんと大層盛り上がって、家路に付いたのは午前2時半のこと。
ちなみに翌朝、というかこの朝の起床予定は4時半。
それでも帰宅してきっちり風呂に入って(健康上あまりよくないですよね)、居間のソファの上で束の間の睡眠に入ったのでした。
たくさんの偶然とそして出会いとに囲まれた、こんな晩もあります。